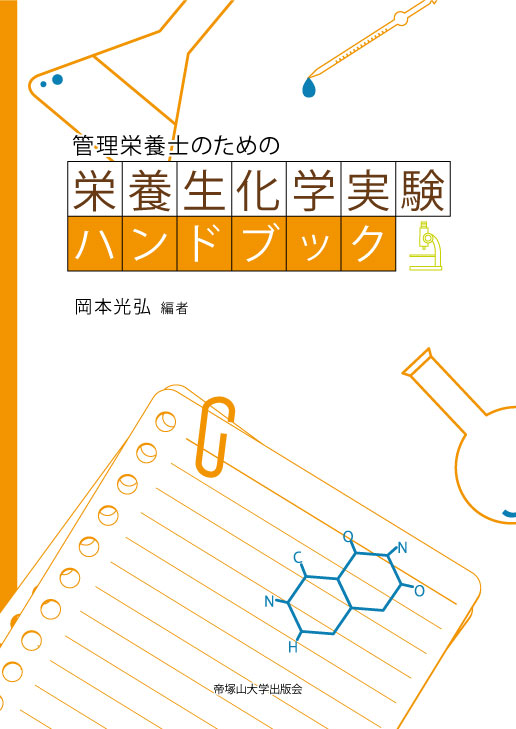帝塚山大学出版会
書籍の紹介
MENU
内容紹介
ヒトは炭素、水素、酸素、窒素の4つの元素が結合した有機物質を含む食物を食べ、身体の中でこれらの有機物質を分解して炭素と酸素から炭酸ガスを、水素と酸素から水を、そして炭素、水素、酸素、窒素の4つの元素から尿素を作ってそれらを排泄します。
食事から排泄に至るこの過程においては、4つの元素の間の結合の組み替え反応が絶えず起こっています。組み替え反応において発生するエネルギーの一部はヒトの身体活動に利用され、残りは身体成分を再構成するのに用いられます。
これらの過程全体はまとめて栄養と呼ばれます。管理栄養士養成課程においては「生理解剖学」、「生化学」、「基礎栄養学」という講義科目で栄養の仕組みについて詳しく学びます。
そして講義で得られた知識を実験によって確かめるために「解剖生理学実験」、「生化学実験」、「基礎栄養学実験」などの実験科目を履修することが必要です。3つの実験科目のうち「生化学実験」と「基礎栄養学実験」は実験内容の関連性が深いので、この本では「栄養生化学実験」という言葉を使いました。
この本は管理栄養士養成課程の学生が生化学実験と基礎栄養学実験を行うときにハンドブックとして利用できるように編集しました。まず最初に試薬溶液の作成や分光分析法など、生化学関連の実験のすべてに共通する基本項目について解説しました。
その後3大栄養素の性質とそれぞれの消化を調べる実験を解説しました。そして次に栄養素の代謝に重要な役割を持つ酵素のうち学生実験に適した3種類の酵素についての実験を解説しました。最後に動物を使った栄養生理学的な実験について述べました。「基礎知識編」においては実験を行うのに最低限必要な知識を簡単にまとめました。学生4名からなるグループが1つの実験項目を1回、約2時間で終了できるように解説しました。
これらの実験は、著者たちがそれぞれの教育施設において、学生の実験グループの編成や実験施設の整備状況を考慮した上で、実験実施項目を取捨選択して実践しているものです。 1学期間に行われる実際の授業の進行においては、実験を実施する授業時間のほかに、実験結果をまとめてレポートを作成する授業時間や、実験データの発表を行う授業時間などを設定する必要があります。
詳細内容
目 次__
実験準備編 第1 章一般的注意事項 ..............................................................................3
1-a. 実験を始める前に .......................................................................................3
1-b. 実験中に ...................................................................................................4
1-c. 実験終了後に .............................................................................................5
1-d. 実験ノートとレポートの作成 ........................................................................5
第2 章基本的な実験器具と分析機器 .........................................................6
2-a. ガラス器具とピペット:取り扱うときの常識、洗浄法 .......................................6
2-b. 主な分析機器 .......................................................................................... 12
実験編
第3 章試薬溶液の作成 ........................................................................... 21
3-a. 0.9%(w/v)塩化ナトリウム(NaCl)水溶液(生理的食塩水)100 ml の作成 ...... 21
3-b. 1 mol/l 水酸化ナトリウム(NaOH)水溶液100 ml の作成 .............................. 22
3-c. 0.2 mol/l リン酸一水素カリウム水溶液300 ml の作成 ....................................... 23
第4 章リン酸緩衝液 .............................................................................. 25
4-a. リン酸水溶液のpKa の決定 ........................................................................ 25
4-b. 0.2 mol/l リン酸緩衝液(pH6.8)の作成 ...................................................... 27
第5 章中和滴定 .................................................................................... 29
5-a. シュウ酸水溶液の水酸化ナトリウムによる中和滴定 ....................................... 29
5-b. 食酢に含まれる酢酸の定量 ........................................................................ 33
第6 章吸収スペクトルと分光分析法 ...................................................... 35
6-a. メチルオレンジ水溶液の吸収スペクトル ...................................................... 35
6-b. NAD+ とNADH 水溶液の吸収スペクトル ...................................................... 37
6-c. タンパク質溶液の紫外部吸収とタンパク質濃度の測定 .................................... 40
第7 章糖質の実験 ................................................................................. 43
7-a. 糖質の定性反応 ....................................................................................... 43
7-b. デンプンの塩酸による加水分解反応 ............................................................ 45
7-c. デンプンのアミラーゼによる消化反応1:酵素量の影響 .................................... 47
7-d. デンプンのアミラーゼによる消化反応2:還元糖の定量(ソモジ・ネルソン法) ... 51
第8 章アミノ酸の定性反応 ..................................................................... 54
第9 章タンパク質の実験 ........................................................................ 56
9-a. タンパク質の変性 .................................................................................... 56
9-b. タンパク質の塩析 .................................................................................... 57
9-c. タンパク質の等電点沈殿 ........................................................................... 58
9-d. ビウレット反応によるタンパク質の呈色反応 ................................................ 60
9-e. ローリー法によるタンパク質の定量反応 ...................................................... 61
9-f. タンパク質のプロテアーゼによる消化反応 ................................................... 62
第10章脂質の実験 ................................................................................. 67
10-a. 肝臓に含まれる脂質の抽出(ホルチ法) ......................................................... 67
10-b. 中性脂肪の定量 ....................................................................................... 68
10-c. コレステロールの定量 .............................................................................. 71
第11章酵素の実験 ................................................................................. 73
11-a. アルカリホスファターゼ ........................................................................... 73
11-b. 乳酸脱水素酵素 ....................................................................................... 82
11-c. グルコース6- ホスファターゼ .................................................................. 85
第12章グリコーゲンの蓄積におよぼすホルモンの作用 ........................... 88
第13章アミノ酸の腸からの吸収 ............................................................ 91
基礎知識編
14. 物質、分子、原子 .................................................................................... 97
15. 溶液中の物質の濃度の表し方 ..................................................................... 98
16. 電解質の水溶液の性質と水素イオン濃度(pH) ............................................. 98
17. 分光分析法 .............................................................................................103
18. 糖質の性質 .............................................................................................105
19. アミノ酸の性質 .......................................................................................111
20. タンパク質とペプチド結合 ........................................................................115
21. 脂質の性質 .............................................................................................116
22. 酵素の性質 .............................................................................................117
付録編
(1) 主な元素の周期律表 ....................................................................................121
(2) 指数 .........................................................................................................121
(3) 単位の接頭語 .............................................................................................122
(4) 対数 .........................................................................................................122
(5) ギリシア文字 .............................................................................................122
お問い合わせ
- 帝塚山大学出版会
-
〒631-8501 奈良市帝塚山7-1-1
TEL 0742-48-9122 FAX 0742-48-9030 - shomu@jimu.tezukayama-u.ac.jp