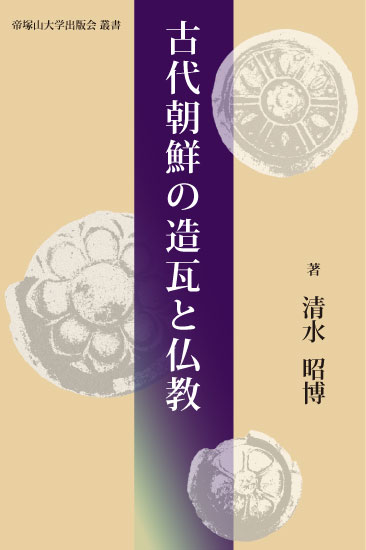帝塚山大学出版会
書籍の紹介
MENU
内容紹介
本書は日本に造瓦技術を伝えた古代朝鮮の造瓦の歴史や、造瓦と仏教の関わりについて解説している。
日本の造瓦技術は6世紀末、日本最初の本格的な仏教寺院である飛鳥寺(奈良県明日香村)の造営に際し、百済から伝えられた。その後、藤原宮(奈良県橿原市、694~710年)で初めて宮殿に瓦が採用されるまでの約1世紀のあいだ、瓦は仏教寺院の独占物であった。いわば、寺院の象徴でもあったのである。
本書では、こうした日本に造瓦技術が導入された歴史を踏まえ、古代朝鮮の楽浪、百済、新羅の造瓦技術の諸相について研究し、古代朝鮮における造瓦技術と仏教との関わりに言及している。
詳細内容
目次
まえがき
第I部 古代朝鮮の造瓦史 1
はじめに 3
第一章 高句麗 7
第二章 百済 25
第三章 新羅と伽耶 55
第四章 まとめ―古代朝鮮の造瓦史― 77
第II部 古代朝鮮の造瓦の諸相 103
第一章 楽浪土城の造瓦技術 105
第二章 古新羅瓦の源流 143
第三章 百済外里遺跡の鬼形文塼 157
第四章 日本における百済瓦工の足跡 171
第III部 古代朝鮮の造瓦と仏教 193
はじめに 195
第一章 高句麗 197
第二章 百済 207
第三章 新羅 221
第四章 まとめ 235
第IV部 中国南朝の瓦 247
あとがき 291
初出一覧 293
お問い合わせ
- 帝塚山大学出版会
-
〒631-8501 奈良市帝塚山7-1-1
TEL 0742-48-9122 FAX 0742-48-9030 - shomu@jimu.tezukayama-u.ac.jp