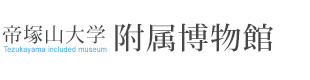特別展示
![]()
- ホーム
- 特別展示
- 2010年過去の特別展示一覧
- 第13回 特別展示 「平城遷都千三百年記念 瓦工場群出現」
第13回 特別展示 「平城遷都千三百年記念 瓦工場群出現」
平城遷都に伴って、大極殿をはじめとする壮大な建物が数多く建てられました。その建物に葺き上げる瓦は、およそ700万枚必要だったろうとの計算もあります。その瓦生産の場所として、奈良山丘陵が選ばれました。ここには良質な粘土、豊富な谷川の水があり、そして燃料となる灌木が生い茂っていました。瓦窯を築く絶好の地でした。おそらく、平城宮予定地で地鎮祭が行われた直後から窯を築きはじめ、夜を日に継いで瓦作りの作業が続けられたことと思われます。この地では、奈良時代を通じて瓦生産が行われました。
| 展示/開催期間 | 平成22年10月4日(月)~ 10月30日(土) |
|---|---|
| 休館日 | 日曜・祝日(但し、10・11日は大学祭のため開館します) | 展示解説 | 10月5日(火)・11日(月) 13:20~ 10月23日(土)・30日(土) 15:45~ |
| 関連講座 |
市民大学講座 ※ 各回 14:00~15:30 |
| その他・資料 | その他・資料 |
-

- 平城宮初期の軒瓦(丸瓦)
-

- 平城宮初期の軒瓦 (平瓦)
過去の特別展示
- 2026年過去の特別展示一覧
- 2025年過去の特別展示一覧
- 2024年過去の特別展示一覧
- 2023年過去の特別展示一覧
- 2022年過去の特別展示一覧
- 2021年過去の特別展示一覧
- 2020年過去の特別展示一覧
- 2019年過去の特別展示一覧
- 2018年過去の特別展示一覧
- 2017年過去の特別展示一覧
- 2016年過去の特別展示一覧
- 2015年過去の特別展示一覧
- 2014年過去の特別展示一覧
- 2013年過去の特別展示一覧
- 2012年過去の特別展示一覧
- 2011年過去の特別展示一覧
- 2010年過去の特別展示一覧
- 2009年過去の特別展示一覧
- 2008年過去の特別展示一覧
- 2007年過去の特別展示一覧
- 2006年過去の特別展示一覧
- 2005年過去の特別展示一覧
- 2004年過去の特別展示一覧